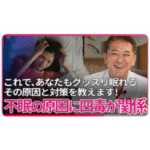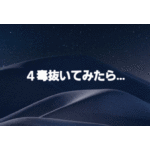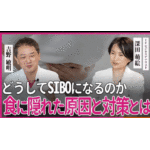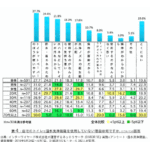甘い物中毒
 oO☆゜.。+o●☆.。+oO☆.○。o∞○。○o’●oO☆゜.。+o●☆.。+oO☆.○。o∞○。○o’●
oO☆゜.。+o●☆.。+oO☆.○。o∞○。○o’●oO☆゜.。+o●☆.。+oO☆.○。o∞○。○o’●
いつぞやに「糖質依存などない」といった記事を投稿しましたが、食や医療に詳しい吉野敏明先生が“甘いもの中毒”について街頭演説の中で説明していましたので、熟慮してみたいと思います。
果物の原種は甘くない
甘い物は自然界にはほとんどないという。果物の原種は甘くないという。スイカを例にとると、1600年代から1700年ぐらいまでのスイカはグレープフルーツくらいの大きさで半分に切ると白い部分が2/3で赤い部分は1/3程度で種がぎっしり詰まっていたたという。甘さはほとんどなく、キュウリの仲間であることを証しています。
柿も原種は全く甘くないそうです。イチゴも昔は酸味が強く、甘さが少なかったために砂糖と牛乳をかけ、潰して食べるのがポピュラーであったのを思い出させてくれました。糖度は昔の17倍にもなっているそうです。
果物はビタミン、ミネラル、果糖でできていたが、糖度が上がるということは蔗糖とかブドウ糖が高くなるということだと説明しています。
農家がよく用いる手法として、意図的に水を与えないようにしていると、命を絶つことになる為、種を絶やさないように食べてもらって、種を含んだ糞便を様々なところに蒔いてもらうために、糖度が上がるという。もちろん品種改良も行われてきたと説明しています。
今はほぼメロンの昔のプリンスメロンはほとんど瓜だったことを思い出させてくれました。グレープフルーツも昔は砂糖をかけて食べていました。
植物と動物の密接な関係
大昔というかもともとは甘い物はほとんどなかった。しかも種類を問わずほとんど秋に実るという。或いはブドウのように雨季が終わって乾季を迎える時期に成るものもあった。それは種を残すために、食べてもらって糞便で蒔いてもらう自然の仕組みの一つだという。
動物は植物を食べて種を蒔く。植物は食べてもらうために定住する。肉食動物も草食動物を食べるために動き回る。植物は空気中の二酸化炭素を合成して、有機物を作るのが目的だという。植物が動き回ると草食動物が食べに来てくれない、食べられやすいように定住している。動物と植物は全くの裏返しだと説明しています。
つまり炭水化物を作るために二酸化炭素を吸収して動かない、自分たちが作った炭水化物を食べてもらって、動物がエネルギーに変えて二酸化炭素を排出して、それを植植物が吸って…という循環を繰り返している。動物と植物は常に対になっていて両方が必要な数で組織しないと成り立たないという。
そして種を含んだ糞を撒き散らしてもらう時期が日本の場合秋なのです。秋に撒かれたそれは冬の乾季に土中に埋まっていて春に雪解け水や雨によって膨らみ芽を出すという循環を繰り返していると説明してます。そしてこれが本当のSDGsだと加えていました。
甘い物は別腹?

動物は甘い物が大好きだという。たくさん食べると満腹になって食べるのを止めるという回路が働く。しかし、甘い物においてはこの回路を作ってはいけない、どんどん食べさせて、中性脂肪を作り、肝臓にグリコーゲンとして蓄え、皮下脂肪として蓄え、内臓脂肪として蓄え、血中にコレステロールの形で蓄積させる、そして太りまくる…。どんなにお腹いっぱいでも甘い物を食べるという回路があるという。
これには味を感じる味蕾というものが舌に存在するが、甘みを感じる味蕾は舌以外にも食道や幽門、十二指腸まで存在するという。つまり甘い物を食べると4回美味しいという。満腹中枢は働かず「甘い物は別腹」の理屈だという。
過食症で食べ吐きしている人は8回至福感を味わっているというが、これについては些か頷けません。
人間以外のリス、ウサギ、ネズミ、日本ザルは食べ食べて食べまくってお腹いっぱいになっても頬にあるエサ袋にためるという。
砂糖を摂ると脳の快楽報酬系という回路が働いてA10神経というところに入って、大脳新皮質の前頭前野からドーパミンが出る。回路は覚醒剤と同じだというが、砂糖には幻聴や幻覚はありません。
甘い物を食べまくって太ります。ドーパミンによって多幸感が生まれるが、時間の経過とともに陰鬱とか悲しみという感情が出てくる。そこでまた甘い物を食べるとそれらが解消され、また悲しい。これを繰り返して感情の起伏が激しい状態に陥る。
もともと虚証という体力がなくて悲しみが出る傾向の人は甘い物を食べれば食べるほど鬱病がひどくなるという。
健康を売りにしたものを食べて甘い物中毒に陥っている人もいるという。鬱病の入院患者は「甘い物を食べているわけではなく、乳酸菌を」「甘い物を食べているわけではなく食物繊維を」「甘い物を食べているわけではなくビタミンとミネラルを」と言い訳しながら否定することが多いらしい。
企業側も色々な効能を謳っては甘い物を売っている。しかしこれが習慣を生み、中毒をもたらすという。
野生動物の場合すべての餌を食い尽くすと悲しいとか陰鬱という感情が起こって終わる。すると引き籠り、冬眠を行うが、これが冬眠の理屈だと語っています。
そしてその悲しみという状態が抜けるのが、甘い物断ちして3か月を要し、ちょうどその頃春を迎え冬眠生活を終えるという。
品種改良によって甘みが強くなることで、甘さに対する中毒に拍車がかかっているという。しかもコンビニで売られている菓子などは季節に無関係のため冬眠による甘い物断ちが行われず中毒が延々と続くのです。
単糖類の吸収される器官
蔗糖やブドウ糖といった単糖類は口腔粘膜で吸収されるという。自然界にない精製糖を食べると血糖値が自然界では起こりえない高血糖となるため、緊急事態に対して自然界では絶対に使われないインシュリンというホルモンが膵臓から分泌され、血糖値が一気に下がり、下がり過ぎてしまうと副腎からグルカゴンやコルチゾールが分泌されて血糖を再び上げようとする。するとこれを抑えようとインシュリンが出、乱高下を繰り返し、感情の起伏を激しくさせる。
グルカゴンやコルチゾールは疲労のホルモンであり、発がん性も高いため、多くのガン患者は甘い物好きだという。砂糖が悪いのではなくホルモン異常だと明言しています。
ご飯

ご飯は澱粉なので口腔粘膜からは吸収されない。しかも、よく咀嚼するとペプチドグリカンが分泌され口内をコーティングしてくれ、口腔粘膜からの吸収を阻害してくれるという。つまり澱粉がアミラーゼによって麦芽糖に分解されても、急激な血糖値の上昇につながらないという。
十二指腸に辿り着いて、マルターゼによってようやく麦芽糖がブドウ糖に分解され、小腸で吸収が始まる。つまり、ご飯を喫食後十数時間経過してから吸収をするので血糖値はゆっくり上昇するのです。
ところが咀嚼が少ないと、膵臓から大量にアミラーゼを出すことになり、急性膵炎を引き起こしやすいという。
よく咀嚼しなければならない玄米と焼き魚などを食べていれば病気にならないという。おかゆを食べる場合も良く噛まなければ消化に良くないので咀嚼することを推奨しています。
果物の食べ方
現世の甘過ぎる果物を食前に食べるのはNGだという。おやつにお菓子よりましだと思って食べるのも推奨できないと言っている。ペプチドグリカンでコーティングされた口で食後にデザートとして少量食べるのが理想だとよしりんは言っています。
当サイトでもあしらい程度が理想と記しています。
朝ごはん代わりに果物食べている人は色々な病気になるという。がんの人はすごく多いそうです。食間もやめて食後に少量食べることで血糖値がさらに遅れて下がるのでお勧めだそうです。
フェアトレード
巷で売られている廉価なチョコレートの原料のカカオは3歳から5歳の子供を誘拐してきて名前もつけず、教育も受けさせず奴隷としてこき使い、収穫しているという。奴隷なので給料は支払われず、こき使っているので寿命は12歳くらいだそうです。農家の人を使っていないので人件費は0円。巷の廉価なチョコレートを食べている人は誘拐、奴隷、人種差別、人殺しとかに加担していることの認識を促しています。コーヒーも同様だという。
これを是正すべくフェアトレードが生まれたという。巷の280円くらいのチョコレートがフェアトレードのチョコレートだと3,000円ほどにもなるという。つまり元来は高級な嗜好品で毎日食べられるものではないと語る。
フェアトレードのコーヒーだと1杯2,000円くらいだという。
つまり、そういった安い嗜好品を食べるということは自分が病気になるだけではなく、誘拐、奴隷、人種差別、人殺しに加担しているということを自覚してほしいとよしりんは訴えてます。
最後に甘い物は病気になったり、社会不安を起こしたり、治安を悪くしたりする食べ物だという。サトウキビなども江戸幕府まではかなり制限していたという。
中国は精製された小麦による餃子や小籠包、中華麺、中華まん、砂糖キビを精製した白砂糖で甘い物も作っている。アヘンを生成したヘロインもアヘン戦争で歴史に記されているとおり…など精製した物はすべてΦザーが行い、中国に売りつけたものだという。
みなつながっていると教えてくれました。
最後に精製はしてはいけないと締め括っています。こういうことを歴史的に科学的に動物学的に生命科学的に解っていたら、現世のおかしさに気が付くはずだと、こういうことを教えないから子供たちは学校でお菓子を食べている、延いてはガンになっていると警鐘を鳴らしています。







 ☞サイトマップはこちら
☞サイトマップはこちら