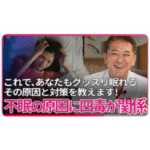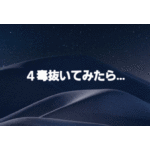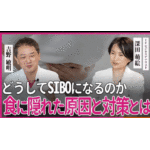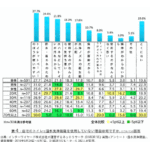太らないおかず色々①
oO☆゜.。+o●☆.。+oO☆.○。o∞○。○o’●oO☆゜.。+o●☆.。+oO☆.○。o∞○。○o’●
クッキング編でもっと身近なおかずをというリクエストに応え、何点か用意してみることにしました。
小松菜のわさび和え(4人前)

【材料】
┏茹でて絞った小松菜 100㌘
┠茹でて絞った千切り人参 8㌘
┠濃口醤油 8㌘
┠上白糖 4㌘
┠練り山葵 1.2㌘
┠粉末鰹だし 0.4㌘
┗食塩 少々
【作り方】
①小松菜を1分ほど茹でて水にさらし、水気を切って絞ります。2.5㌢㍍ほどのざくぎりにしておきます
②人参の千切りも同時に茹でて水にさらし、水気を切って絞ります
③合わせた調味料で①∔②を会えます。
※調味料が混じり合いにくかったら加熱して溶けた合わさったものを冷やしてまぜます
![]()
ひじきと大豆の煮物(15人前)

ひじきの煮物と言えば通常油で炒めてから作るのが定番となっていますが、炒めなくても何の問題もなく美味しくできますので、ここでは炒めません。
【材料】
┏水で戻した芽ひじき 50㌘
┠大豆水煮 150㌘
┠千切りこんにゃく 100㌘
┠茹でた千切り人参 50㌘
┠水 200㌘
┠鰹だし 5㌘
┠濃口醤油 50㌘
┠みりん 15㌘
┗上白糖 30㌘
作り方
①芽ひじきを水に戻しておきましょう。長ひじきは見た目にも味的にも野性的ですのでこの料理には向きません
②こんにゃくと千切り人参は千切りにして茹でてアク抜きをしておきます
③みりん以外の水と調味料で①+②を水気がなくなるまで混ぜながら煮ていきます
④水気がなくなる直前でみりんを入れ照り付けます
⑤水気がなくなり照りが付いたら出来上がりです
豆腐を使ったマネヨーズ
別の章でも述べましたが、マヨネーズを真似たのでマネヨーズです。日本料理で使う白酢は練り胡麻を使い美味しいのですが高脂肪で酸化しやすいので、ここでは真っ当に卵黄を用います。
【材料】
┏木綿豆腐 350㌘
┠レモン果汁 50㌘
┠穀物酢 10㌘
┠卵黄 37㌘(2個分)
┠砂糖 10㌘
┠食塩 5㌘
┠顆粒だし 4㌘
┠練り辛子 3㌘
┗牛乳 少々
作り方
①木綿豆腐がなければ絹でも大丈夫です。まな板の上に置き、布巾を乗せ、さらにその上に水の入ったボールを乗せ、斜めに傾けて水切りをします

②①と残りの材料全部をフードプロセッサーにかけて出来上がりですが、固さは牛乳で調整します
![]()
かぼちゃサラダ(4人前)
【材料】
┏茹で(蒸し)かぼちゃ 120㌘
┠玉葱みじん切り 24㌘
┠豆腐マネヨーズ 64㌘
┠食塩 少々
┠上白糖 少々
┗胡椒(白) 少々
作り方
①カボチャを加熱します
②①を進めている間に玉ねぎのみじん切りを塩かそばつゆなどで和えておきます
③①潰せるほどに火が通ったら潰して、冷凍庫などで凍らないように冷まします
④②を布巾などで固く絞ります
⑤③④と調味料を混ぜ合わせます
![]()
ミートソース(4人前)

油で炒めない茹でたてのパスタで食べます。
もちろんご飯で食べても、パンで食べても美味しいのですが、一人前数量より少なく、食べられる方が望ましいです。もっとも連日食べるのでなければ気にすることはありません。
【材料】
┏豚もも挽肉 80㌘
┠玉葱みじん切り 120㌘
┠人参みじん切り 40㌘
┠にんにく 2㌘
┠水 240㌘
┠赤ワイン 40㌘
┠粉末鰹だし 4㌘
┠トマトケチャップ 160㌘
┠トマトペースト 4㌘
┠濃い口醤油 20㌘
┠中濃ソース 20㌘
┠食塩 4㌘
┠胡椒 少々
┗片栗粉 8㌘
【作り方】
①豚もも挽肉を塊にならないよう水を張った鍋に入れて攪拌しながら加熱していきます。浮いてきた灰汁は取り除いてください
②①に火が通ったら鍋ごと氷水か冷凍庫で冷やし、浮いた油を取り除きます
③玉葱みじん切り、人参みじん切りと片栗粉以外の調味料を②の鍋に入れ、攪拌しながら再度加熱します
④沸騰してきたら一旦火を止め分量分の片栗粉を水で溶き、鍋に入れたら焦げ付かないようヘラで鍋底をこすりながら再加熱をし、再沸騰して1分ほど続けたら火を止めて出来上がりです
料理の仕方を公開するのは大いに結構なのですが、一人前の量、一食の量を掌握するのは本人に委ねなければならない部分もあります。
本来何を一緒に食べるのか、何を一緒に飲むのか、ご飯をどれくらい食べるのかで微調整が必要になってくるのですが、腹八分目の感覚は人それぞれによりますし、食べる速度によっても変わってきます。
基本的な目安を示しているセオリーはたくさん見かけますが、普段の食生活の中で是非コツと自分の量を掴んでほしいと思います。







 ☞サイトマップはこちら
☞サイトマップはこちら